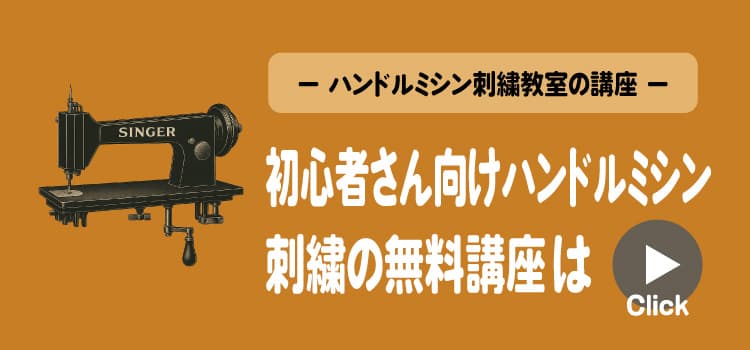ハンドルミシンとは?

右手でテーブル下のハンドルを回し、刺繍の進行方向を自在に操作できるミシンです。時計回り・反時計回りに360度回転します
これをユニバーサルフィード機構と呼びます(後述)
Lintz & Eckhardt、Singer、Cornelyの3社は、19世紀後半から20世紀初頭にかけて発展した工業用チェーンステッチミシンの設計・製造に深く関与した企業であり、それぞれが独自に発展しつつ、互いに技術的な影響を及ぼしあった歴史があります。最初のチェーンステッチミシンの原型を発明したBonnazからの系譜を考察します。
このコラムではSInger,Cornely,Lintzの歴史的な背景とその各モデルについて書いてみました。
基本的な事前情報として
チェーンステッチとは
チェーンステッチ(環縫い)とは、糸が連続して鎖(チェーン)のような形に絡み合いながら縫われる縫製方法です。和名では「環縫い(かんぬい)」とも呼ばれます。
アメカジやヴィンテージジーンズが好きな方は裾を見てみてください。チェーンステッチで縫われているはずです。
誰でも装飾できたチェーンステッチ
1本の糸をルーパー(またはかぎ針)が動かし、前の縫い目のループに次のループを通して絡ませることで形成されます。
シャトルやボビンを使わずに済むのも特徴です。
1本の糸のみで装飾が作れるメリットがある一方で、解けやすいため、耐久性が必要な縫製には不向きです。また縫い終わりの処理が甘いとほつれやすいです
装飾としてのチェーンステッチ
当時は服飾に装飾を施すには、1本の糸で表現できるチェーンステッチが重宝されていました。また現代のように様々な種類の手刺繍の技法は未成熟でした。
装飾は手刺繍で行っており、大量に装飾を施すには時間がかかりました。
時代を経て再評価されるチェーンステッチ
現代からの視点であれば、糸は1本しか要らず、簡単で、誰でも装飾できるチェーンステッチは、刺繍の技術としては黎明期の技術であり、敢えてチェーンステッチに拘る必要なないように思えます。
ただ、シンプルな技法になればなるほど、縫い手の技術が試され、個性が糸目に現れます。
当時の会話でもきっとこのようなシーンはあったはずです。
【この縫い方は〇〇さんのね】
【この糸目の感じは〇〇さんのね】
現代では100年前とは技術革新も大きく進み、昨今ではAIの登場でもはや誰でも簡単に高度な技術を借りて、さまざまな表現が実現できるようになりました。
この技術革新が突き進んだ先の表現はどうなっていくのでしょうか。
刺繍から作りの顔が見える表現は残るのでしょうか。
歴史について(SInger114w103にフォーカス)
ミシンが普及していく歴史的な背景
刺繍と装飾縫いの需要増加(20世紀初頭)
19世紀中頃までの刺繍は基本的に「完全な手作業」でした。
1900年代初頭、洋服やインテリア製品(カーテン、テーブルクロスなど)において装飾ステッチの需要が急増していました。
チェーンステッチは、柔らかく立体感のある美しい縫い目で人気でした。
その一方で、手縫いでのチェーンステッチは時間がかかるため、機械化が強く求められていました。
シンガー社の工業用部門 114Wシリーズ
シンガー社は、ニュージャージー州エリザベスの「W工場(Wheeler & Wilson由来)」で工業用ミシンを製造していました。
「114Wシリーズ」は、その工場で開発された装飾縫い専用の工業用モデル群。
114W103はその中でも代表的で、シンプルな1本糸の環縫い(チェーンステッチ)を高精度で行える設計になっています。
ちなみに、114Wシリーズには、101,102,103,104,105,106,107の少なくとも7種類が確認されています。
特徴的な機構の革新
- 手動ガイドまたはジグにより、自由なカーブ縫いが可能(フリーモーション対応)
- ルーパーとカムによるステッチ形成(シャトルやボビンを使用しない)
- 非常に高速なステッチ速度(当時の手縫いの何十倍)
用途:刺繍、モノグラム、ワークウェアの装飾など
- ワークシャツ、ジーンズ、ユニフォームなどの装飾チェーンステッチに使われました。
- 特にアメリカでは、ワークウェアブランド(例:Levi’s、Ben Davisなど)の刺繍に活用。
Cornely(コーネリー)とSInger114w103の関連性
深い関連がありますが、両者は別のブランドでありながら、目的や構造が類似したチェーンステッチ刺繍ミシンです。
歴史的背景
Cornelyミシンが先に開発されており(19世紀後半)、その技術や仕組みを参考にしてSinger社がアメリカ市場向けに114W103を開発した可能性が高いです。特許の関係もあったはずです。(後述します)
つまり、Singer 114W103はCornelyの発想を取り入れたアメリカ版刺繍ミシンと見ることができますね。
| 項目 | Singer 114W103 | Cornely ミシン |
|---|---|---|
| 製造国 | アメリカ(Singer社) | フランス(Cornely社) |
| 開発年代 | 1911年頃 | 1860年代(Cornely A型など) |
| 主な用途 | フリーハンド刺繍(チェーンステッチ) | 同上(特に装飾刺繍・マルチコードワーク) |
| ステッチタイプ | チェーンステッチ、モスステッチ | チェーン、ループ、モスなど多様なステッチ |
| 操作方法 | クランク操作(自由に布を動かす) | 同様(手動で方向を調整) |
| 工業用としての展開 | 限定的(主にアメリカ) | ヨーロッパを中心に広く使用 |
CornelyとSingerの類似点
どちらも自由な動きで複雑な刺繍ができるミシンでチェーンステッチや装飾的な縫い目が可能。ただし操作には高度な技術が必要。
CornelyとSingerの違い
Cornelyのほうが高機能なモデル展開が多く(例:コードフィード機構、ループステッチ機能など)、装飾技法に特化して発展してきました。
Singer 114W103は比較的シンプルなチェーンステッチ専用機として設計されました。
Cornely代表モデルとSinger 114W103の比較
| 項目 | Singer 114W103 | Cornely A | Cornely B | Cornely L |
|---|---|---|---|---|
| 製造国 | アメリカ | フランス | フランス | フランス |
| 開発時期 | 1911年頃 | 1860年代 | 1900年代初頭 | 20世紀中頃 |
| ステッチ種別 | チェーンステッチのみ | チェーンステッチ | チェーン+コード刺繍対応 | ループステッチ(立体感あり) |
| 主な用途 | 装飾・刺繍 | 装飾・モノグラム | コード刺繍・装飾 | 毛羽のある装飾(パイル風) |
| コード装着 | 不可 | 不可 | 可能 | 一部可能 |
| 操作方法 | ハンドクランク(布を手で操作) | 同上 | 同上 | 同上 |
| 現存数 | 少数(特に整備済み) | 比較的多い | やや少ない | レア |
| 特徴 | 頑丈・シンプル・操作性高い | 元祖的存在 | 多機能・職人向け | 立体刺繍対応 |
Lintz & Eckhardt(リンツ・エッカルト)
会社の歴史と技術革新
Lintz & Eckhardtは1877年に設立され、チェーンステッチ刺繍ミシンの分野で先駆的な存在となりました。彼らのミシンは、従来の手刺繍に比べて大幅な効率化を実現し、1分間に最大3000ステッチを可能にしました。これは、手作業の25ステッチと比較して飛躍的な進歩でした。
また、Lintz & Eckhardtは、Cornely社の「Machine A」に類似したモデルも製造しており、チェーンステッチやモスステッチといった多彩な刺繍が可能でした。これらのミシンは、カーテン、衣類、リネン製品など、さまざまな素材への装飾に使用されました。
第二次世界大戦後、1952年にLintz & Eckhardtは東ドイツ政府により国有化されました。しかし、創業者は戦前に17台のミシンや多数の部品、マニュアルなどを自宅の屋根裏に保管しており、それらは戦争を乗り越えて現存しています。
現在でも、Lintz & Eckhardt製のミシンはヴィンテージ市場で高く評価されており、特にCornely A3と同等の機能を持つモデルは、コレクターや職人の間で人気があります。
これらのミシンは、デニムやレザー製品への装飾にも適しており、現代のカスタムファッションにも活用されています。
Lintzの代表的なモデルとCornelyとの比較
Lintz & Eckhardt No. 3(Cornely A3相当)
- 特徴:1910年頃に製造されたモデルで、Cornely A3と同等の機能を持ちます。
- 用途:チェーンステッチによる装飾刺繍に適しており、特にデニムやレザー製品への装飾に使用されました。
- 現存例:ヴィンテージ市場で取引されており、コレクターや職人の間で人気があります。
Lintz & Eckhardt Cornely B(Cornely B相当)
- 特徴:Cornely Bと同等の機能を持つモデルで、チェーンステッチ刺繍に特化しています。
- 用途:衣類やインテリア装飾品への刺繍に使用されました。
- 現存例:現在でも動作可能な状態で取引されており、特にアメリカ市場での需要があります。
Lintz & Eckhardt 151(Singer 114w103相当)
- 特徴:1967年にベルリンで製造されたモデルで、チェーンステッチとモスステッチの両方に対応しています。
- 用途:多用途に使用可能で、特に衣類や装飾品への刺繍に適しています。
- 現存例:完全に修復され、現在でも使用可能な状態で販売されています。
LintzやCornelyのモデルはこちらに多く掲載があります。こちらから
歴史について(チェーンステッチミシン全体)

チェーンステッチミシンの発明者、販売経路、特許が国を超えて発展していった歴史を知るきっかけになれば、嬉しいです
時系列でまとめていくと、実はÉmile Cornely(エミール・コルネリー)のCornelyミシンが普及していく背景には、Antoine Bonnaz(アントワーヌ・ボナズ)のBonnazミシンの存在がありました。
Bonnazについて
Bonnaz(ボナズ)ミシンとは、コルネリーミシンの原型となった刺繍専用ミシンで、主にチェーンステッチ刺繍を行うために開発されたものです。
19世紀後半にフランスで誕生し、Émile Cornely(エミール・コルネリー)の特許技術をもとに製造・普及しました。
歴史的な資料からは、Cornely A型以前の呼称や機種の通称をBonnazミシンと総称するようです。
つまりBonnazがまずは1863年にフランスでチェーンステッチ機構とユニバーサルフィード機構の特許を取得したのちに、アメリカでチェーンステッチの特許を取得して(米国特許番号83,910、1868年11月登録)Cornelyが同技術を購入・改良した、とされています。
なぜアメリカで特許を取得したのか
ここで、なぜフランス人のBonnazが1868年にわざわざアメリカでも特許を取得したのか、という素朴な疑問がありますよね?
この背景には、単に技術の保護だけでなく、アメリカ市場への進出と特許戦略の一環として明確な意図がありました。
模倣対策として
19世紀後半、アメリカは工業化が急速に進展していた国の一つであり、刺繍や衣類産業も発展していました。その中で、Bonnazはフランスで1863年に特許を取得したものの、他国ではそのまま技術が模倣される危険がありました。
特にアメリカでは、特許権が強く保護される法制度が整っていたため、製造や輸入販売に備えて米国特許の取得が重要だったとされています。
ライセンスビジネスとして
Bonnaz自身は主にヨーロッパ(特にフランス・ベルギー・スイス)で商業展開していましたが、アメリカでの販売代理権や製造ライセンスを視野に入れていた可能性が高いとされています。
アメリカの特許モデル提出の慣習
米国特許庁(USPTO)では当時、「特許モデル」の提出が必要だった(小型動作模型)ため、Bonnazはそれを提出しました。
この提出モデル(現在はスミソニアンに収蔵)を通じて、Bonnazがアメリカ市場に本気だったことがわかりますね。
スミソニアンのアメリカ歴史博物館には、Antoine Bonnazによる1860年代の刺繍ミシンの特許モデル(miniature prototype)が収蔵されています。
Smithsonian Collections Onlineに様々なミシンの画像が見つけることができます。
ほぼSInger114Wシリーズ、特に103の原型を見ることができます。

Bonnazが特許を取得できた様々な理由
- 手縫いでしかできなかったチェーンステッチを、一人で連続的・均質に再現可能になったため。
- ユニバーサルフィード機構(ハンドルで布を自由に操作できる)によって、手描き風の自由な曲線模様が可能となり、芸術的刺繍が量産できるようになったため。
経済的、文化的、芸術的な影響
- オートクチュール(高級仕立て服)から民間装飾へと刺繍技術が普及する。
- スイスのザンクト・ガレン地方などで刺繍工業が急成長する。
- 模倣→改良→独自進化の流れを作り出し、刺繍ミシン市場が世界的に広がる。
- 手刺繍では非現実的だった大判の装飾や複雑なパターンが実用化する。
- オペラ、軍式典、王族礼装などでの使用が拡大する。
豪華に刺繍された洋服は貴族階級のみの特権であり、そもそも当時の一般市民には刺繍された洋服を着る習慣はなかったはずです。
Bonnazミシンは、芸術刺繍の大衆化と工業化の橋渡しを果たしたと言えるでしょう。
SingerはCornely / Bonnazの特許を侵害したのか?
ここで更なる疑問が出てきますね?
それはBonnazがアメリカで1863年に特許を取得し、その後に販路や販売をCornelyが担っていき、時系列的にはその後にSingerがチェーンステッチミシン(114wシリーズ)を開発していきます。
特許取得しているほぼ同じような機構のミシンをSingerがなぜ販売できたのか?です。
これにはCornelyの1863年特許は、20年程度で失効(通常の保護期間)し、Singerが参入した1910年代には無効となっていました。法的には問題ないことが証明されています。
さらにSingerは独自の構造(ウォームギア式送り、押さえ形状)で差別化しており、アメリカ、フランス両者からはSingerがCornelyから訴えられた、という記録はないようです。
加えて業界慣習として、19世紀末〜20世紀初頭のミシン業界では、失効特許を元に新機種を出すのが一般的だったとされています。
実際の2社の影響関係

先入観では両者の間で裁判戦争(笑)になりかねない印象ですが、実際は違っていたことも判明しています
「Cornelyの影響を受けたSinger設計」は業界内で広く認識されていましたが、技術的模倣ではなく独立設計として扱われたようです。
これは法的にも2社間のいざこざもないことからも予想できますね。
一部の研究者は、「Singer 114W103 は Cornely のBonnaz機構をアメリカ式に再構築したものである」と評しています。
つまり、Singerは「Cornelyの特許の上に成り立つ合法的な進化型」を出したと考えられます。
| 時代 | アメリカ刺繍産業の動き | Bonnaz特許の意味 |
|---|---|---|
| 1860年代 | 市民戦争後の産業復興期。装飾縫いや軍服の需要もあった | 技術導入の好機 |
| 1870年代 | 手工芸から機械化への転換期。移民女性の雇用が進む | 小型刺繍機への関心増 |
| 1880年代以降 | Singerなど家庭用ミシン大手が刺繍ミシンの市場調査を始める | Bonnaz技術が基礎に |
1850年からのチェーンステッチミシンの時系列年表
| 年代 | 主要ブランド | 出来事・開発 | 技術・文化的意義 |
|---|---|---|---|
| 1850〜60年代 | - | 手刺繍が主流、機械化の試みが始まる | 布送りとチェーン形成が課題 |
| 1865–68年頃 | Bonnaz(仏) | Antoine Bonnaz がチェーンステッチ刺繍ミシンを発明・特許取得 | 世界初のフリーハンド刺繍ミシン自由な布送りと環縫い機構を実現 |
| 1870年代後半 | Cornely(仏) | Emile Cornely がBonnazの技術を改良・商業化Cornely A型を開発 | 工業用刺繍ミシンとして広く普及開始万博で受賞し国際市場へ |
| 1890年代〜1900年代初頭 | Lintz & Eckhardt(独) | Cornely機を模倣・改良したLintz & Eckhardt 151などの刺繍ミシンを展開 | ドイツ市場にて高精度機として人気装飾縫いやモノグラム用途で活躍 |
| 1910〜30年代 | Singer(米) | Cornelyと同系統のSinger 114W103などを開発・販売 | 耐久性の高いチェーンステッチ刺繍ミシンとして評価全世界へ展開 |
| 1930〜40年代 | 各国で模倣・派生製品が続々登場 | フリーハンド刺繍が世界中に広がる | 刺繍ワークショップや産業が確立 |
| 1950〜70年代 | TREASURE(日本・奈良) | CornelyやSingerの模倣・改良を元に、ESシリーズ(ES-1114等)を製造 | 精密機械として日本国内の刺繍工房に普及奈良を中心に産業化 |
| 1990年代〜 | Brother, Tajima など | コンピュータ刺繍機の普及 | 量産性と自由度が飛躍的に向上 |
| 現在 | Cornely復刻、TREASURE整備品市場 | ヴィンテージ機の価値が再認識される | ハンドル操作の手刺繍的魅力が再評価中 |
SInger114w103の特徴
チェーンステッチ専用
一本の糸でチェーン状の刺繍を施すことができ、独特の立体感とヴィンテージ感のある仕上がりが特徴です。ただしチェーンステッチのみしか(厳密に言うとモス刺繍も可能)できません。※モス刺繍についてはまた別のコラムで寄稿します。
ただし手縫いのチェーンステッチがミシンで自動で刺繍できるようにはなったものの、縫い終わりの糸処理についてはきちんと糸処理が必須となっています。1本刺繍のため、糸処理が甘いとスルスルと全て解けてしまいます。
手動操作
ミシン下部のハンドル(クランク)を手で回すことで、自由に布を動かしながら刺繍を行います。これにより、手描きのような自由なデザインが可能です。
このハンドル操作から国内ではハンドルミシンという呼称が使われていると予想されます。ちなみに海外ではChainstitch Embroidery Machineが一般的です。
高い耐久性
適切に整備された個体であれば、今後80年以上の使用も可能とされています。
これは現代ミシンとは異なって、全体を構成するパーツには、コンピューターが搭載されておらず、鉄のギアやシャフトのみで組まれているためです。
メンテナンスと使用上の注意
部品の入手
針やスプリングなどの部品は、現在でも入手可能な場合がありますが、オリジナル部品の確保や代替品の選定には注意が必要です。
ミシン台の選定
Singer 114W103は一般的なミシンよりも幅が広いため、専用のミシン台が必要です。
既存の台を改造するか、オリジナルの台(困難)を探すことが推奨されています。 一般的には信頼できるミシン店から購入します。
ミシン台をお探しの方はお問い合わせ下さい。Singer114w103を入手するより容易です。
整備の重要性
古いミシンであるため、使用前には専門家による整備や調整が必要です。
無理に整備をするとネジをダメにしてしまう場合もあります。交換パーツがない場合もあるので注意が必要です。
買えるのか?
良い状態が運良く見つけられて、整備されていれば購入できると思います。ただし無理にSinger114w103を購入する必要はないと思います。
正直なところ、ミシンとしてはかなり古いためメンテナンスやコストパフォーマンスを考慮すると、あえてヴィンテージミシンに固執する必要性は高くないのでは?とも感じます。ただやはり往年の歴史あるミシンで刺繍できる喜びは格別です。
追記
2025年9月よりハンドルミシンの代理店を担うこととなりました。お探しのハンドルミシンがございましたら、お気軽にお問い合わせください。
こちらに本体を購入できるページを新たに作りました。
糸目でSinger114w103と判断できる人はいない

これを書いてしまうと、身も蓋も無いのですが(汗)チェーンステッチミシンなので、実際はそうなのです
たかがチェーンステッチ、されどチェーンステッチです。新品のミシンでもできあがってくるチェーンステッチは同じです。
チェーンステッチの糸目を比べて、Singer114w103かどうかの判断をできる人はまずいないと思います。
しかし昨今のSNSの露出や所有している喜び、本物のビジュアル面を打ち出すなどで所有欲が高まる気持ちも充分理解できます。
くどいですが、無理にSinger114w103を入手することは推奨しません。
Singer114w103オリジナルの価格は?
状態によるので、30万から100万(※フルセット)前後かと思います。お探しの場合にはお手伝いできると思いますので個別にお問い合わせ下さい。ただし確実に入手できるとは限りませんので、ご了承ください。
経験的にヘッドオンリーで35万円前後の感覚です。
使えるのか?
状態が良ければ、充分に使えます。古いためそれが逆に今でも使えるということです。状態が悪くとも、きちんと整備することができれば、問題なく使えます。
整備でき、信頼できる専門店を見つける
関東圏、関西圏、アメリカで僕が信頼できる専門店があります。お問い合わせ頂ければ、お繋ぎできます。
中古品を買うのはありなのか?
厳密に言えばオリジナルのSinger114w103は全て中古品になると言い切れるでしょう。ただ個人的にお勧めしないモデルや気をつけた方が良いコピー品も多くあります。
これはSinger114w103の構造が比較的コピーしやすいミシンであるので、アジア圏ではこぞってSinger114w103のコピー品が今でも作られています。
そのコピー品の中でも唯一良いものであると思うのは、奈良ミシンが製造していたTREASURE ES-1114-1です。これはSinger114w103のコピー品の中でかなり良いものだと思います。こちらを使用している方も多くいらっしゃいます。僕の初号機もこちらです。状態の良いTREASURE ES-1114-1を見つけたら、購入を検討しても良いと思います。
海外の粗悪なコピー品に気をつけて
鉄は良質な鉄と粗悪な鉄があります。鋳物がどのように作られているか、原材料の鉄の成分がどのように配分されているか。実はできあがった鉄のミシンに綺麗に塗装されてしまうと、インターネットを通じて画像からは判別できない場合も多いです。
またオリジナルのSinger114w103にそっくりにコピーして、中身を粗悪な部品で組まれたSinger114w103風なミシンがオークション(e-bay)などで今でも多く見つけられます。
さらにプレートのみオリジナルで中身のギア類はコピー品なんて商品もたくさん見かけます。
SIMANCOとは?
SIMANCO = SINGER MANUFACTURING COMPANYの略。
オリジナルにはSIMANCO刻印が数字と共に刻印されています。オリジナルのマニュアルからその数字をたどり、100年以上経った今でもカタログからすべてのパーツを見つけることができます。
大事なことは刻印があることで、それらのパーツは修理可能な部品であり、だからこそ刻印をして純正パーツとして流通させていた、という面です。
そもそもオークションでSinger114w103を購入することはお勧めしません。画像からは先入観で動くと思われがちですが、届いたら部品がなくて全く動かない、その部品も探せず、せっかく購入したのにどうにもならないなんて悲しすぎます。
友人のCharecoソーイングのGiffenが本物と偽物の違いを解説してくれています、字幕オンで理解できる内容です。
現代の仕様にアップデートしても良い
当時は足踏みミシンとして使用されていたので、現代はモーター(サーボモーター)を付けて駆動している方がほとんどです。僕もそうしています。
工業用の本縫いミシンのような本格的なサーボモーターではなく小型軽量のサーボモーターで充分です。
TREASURE ES‑1114シリーズ
おまけとして、トレジャーの情報も書いておきます。
奈良ミシン工業株式会社(ブランド名「トレジヤー(TREASURE)」など)は、大正12年(1923年)に創業され、昭和22年(1947年)に株式会社へ改組、さらに昭和24年(1949年)に現在の社名に変更されたとあります。
奈良ミシン工業(株)は、日本のミシンメーカーであり、TREASURE ブランドを扱っていた企業です(台湾にライセンス譲渡済)。
奈良は古代より針や布織り、刺繍に縁が深く、ミシン工業の背景としても、国内外の技術交流があった地域です。奈良ミシンそのものに関する情報は限られますが、工業都市としての奈良には、ミシン販売・修理の拠点「奈良ミシンサービス」が地域に根付いています。
ES‑1114‑10というモデルもあり、こちらはテープ縫いや編み縫いができるモデルです。
なぜ昔のミシンを使うのか?
ハンドルミシンは、ドイツや日本など各国の工場制手工業の歴史を感じさせる技術で、縫い手の個性や表現力が糸目に現れるのが特徴です。
同じ縫い目を再現できない一回性や、絵を描くような自由な刺繍が可能な点に、ノスタルジーだけでなく深い魅力があります。
大量生産やAI技術が進む現代において、人の手によるものづくりの価値を問い直す必要があります。
当店では、1922〜1940年代製のSINGER 114w103というヴィンテージミシンを使い、あえて非効率な技法で作品を制作しています。その手仕事には、作り手の想いや技術が込められています。
現在はその想いが刺繍教室を開講するというステージになりました。ご興味があればぜひ体験してみてください。
刺繍教室についてはこちらより
この記事を書いた人

渡邉 太地(Taichi Watanabe)